一生に一度のハレ舞台、成人式―その主役にふさわしい装いといえば、振袖です。
あなたも色・柄・素材いろいろ迷いながら・・渾身の1枚を準備されたことでしょう。
そして、袖を通した時の感動の後、この記事を見ていただいているということは予想外の着崩れにお困りではないでしょうか?
そこで!この記事では、着物に親しんで30年着崩れ経験者の筆者がすぐに実践できる着崩れの直し方をお伝えします。どの着崩れが発生しているのか‥すぐに判断できるよう画像付きで解説しています。
大丈夫です!着物は1枚の布でつながっていますので、引っ張ったり紐(ひも)を縛り直したりすることで応急処置ができます。
さらに、着崩れの防ぎ方もご紹介していますので、最後まで読んで頂ければハレの日を無事にお過ごしいただけると思います。是非お役立てくださいね!
【成人式の着物】振袖の特徴と着崩れの原因

★ 袖丈が長い★
<特徴>
成人式で着る着物は「中振袖」という種類
袖の長さ(袖丈)は100cm前後
優雅に揺れる姿は華やかで女性らしい印象
<原因>
袖が何かに引っかかりやすい
座る時に袖を引っ張り、汚れや着崩れ発生
★華やかな柄と装飾★
<特徴>
豪華な柄や刺繡が施されている
生地自体に刺繍がある(地模様がある)ことが多い
<原因>
華やかな分重さがある
腰のひも(腰紐)が緩んでしまうと裾が落ちてくる
着物は身長(背丈)より長い布を、ちょうどよい長さになるよう紐で結んで止めている形ですので、この着崩れが起こると思うように動けなくなります。
★ 帯の結び方が豪華★
<特徴>
刺繡などが施された豪華なものが多い
「文庫結び」「立て矢結び」など様々な結び方(飾り結び)されている
<原因>
豪華な分重さがある
飾り結びが何かに引っかかり形が崩れる
帯を背中に着けている紐が緩むと背中から離れていってしまう
直し方-帯より上
*()内は着物専門用語での呼び方です。
2回目以降は()内の言葉を使って記載させていただきます。
*☆マークは可能であれば実現させたいポイントです。
襟元が緩んでいる・はだけている
着る時に首から胸にかけてしっかり添わせていないと、動いているうちに緩みが発生し
だんだん襟元が開いていきます。長襦袢の衿を綺麗に見せるため、固めの芯が入っていますので無理もありません。着物を着る前に胸元にタオルや綿を当ててふっくらさせておくと発生しにくくなります。
ー直し方ー
1.可能であれば、衿の後ろ中心をピンチ or 洗濯バサミなどで止めておきます。
☆この時、着物の衿の上に長襦袢の衿が出ないようにします。
2.右手で左衿(左前)を持ち、左手は脇の空き(身八ツ口)から手を入れて右衿(下前)を持ちます。
3.「X」になるよう、両手を引っ張り合います。
☆振袖の場合はXの中心が直角(90度)まで合わせます。
4.帯の上側に布が余ってシワが寄っていたら、胸の下にある紐(胸紐)の下側に引っ張って帯の中に入れます。
長襦袢の衿が引っ込む、出すぎる
長襦袢を着た後、着物の衿を合わせるときにXに引っ張りすぎたり、長襦袢と角度が合っていないと動いているうちに長襦袢の白い衿が見なくなってきます。衿を合わせるときにコーリンベルトというゴムを使っていることが多いですが、そのゴムがきついと発生しやすいです。衿の崩れは目立ちますので直しましょう。
ー直し方ー
1.長襦袢(白い衿)と着物の衿の間に人差し指と中指を入れます。
2.指を上から下に動かしながら、ちょうど良い程度長襦袢の衿が見えるよう調整します。
☆ 長襦袢の衿の豪華さと好みによりますが左右の衿が重なっているところで
4㎝程度差があるとよいです。
3.胸のあたりに布が余っていたら、胸紐の下側に引っ張って脇や帯の下に送ります。
直し方-帯より下
裾が上がる・下がる
重力の関係で裾が下がることの方が多いですが、着る時の裾の合わせ方や腰紐の締め具合によって動いているうちに変化しやすい部分です。下がってしまっている場合は紐を締め直したり、上にたくし上げる必要があるので、誰かに押さえていてもらうと直しやすいです。
お近くの方にサポートを頼みましょう。
ー上がっているときの直し方ー
1.腰紐の下に指を入れます。
2.裾の上がってしまっている部分をもって下に引っ張ります。
*これは簡単ですが、引っ張りすぎ注意!です。
*腰紐の下に指を入れないで引っ張るのみだと腰紐も下がってくるので注意です。
ー下がっているときの直し方ー
1.裾の中側(下前)が下がっているときは身八ツ口から手を入れ
裾とつながっている部分(一重上げの部分)を上に引っ張ります。
2.外側(上前)や後ろが下がっているときは、腰紐の上側の布を引っ張ります。
☆ 裾つぼまりになるよう、上前の裾先は下前より3㎝程度UPさせます。
3.腰紐が緩かったら縛り直します。(指1本がやっと入る程度きつく締めます)
腰~お尻のところにたるみがでる
座ったり、立ったりして余分な力が入ると気づいたらお尻部分が膨らんでいることがあります。着物を着なれていないと座るのが大変ですので無意識に引っ張られるのでしょう。
すぐに直せますので、時々鏡やガラスで後姿を確認しましょう。
ー直し方ー
1.布が腰紐の下側に余っている状態ですので、腰紐の上側の布を引っ張って
たるみを無くします。
2.腰紐が緩かったら結び直します。(指1本がやっと入る程度きつく締めます)
3.腰紐の下にシワがよってしまったら、親指で後ろ腰を押さえて左右に広げます。
直し方-帯
帯が背中から離れて落ちそうになっている
こちらは成人式に多い問題です。普通のお太鼓結び(四角い結び方)ではなく、飾り結びをしているときに多く発生します。さらに帯自体が豪華で重いと発生しやすいです。大抵は帯の中に隠されている紐が緩んでしまっているので結び直しましょう。こちらも誰かに後ろを押さえてもらうと直しやすいです。
ー直し方ー
1.帯を背中に止めている帯枕の紐が緩くなっている状態ですので
帯の中に隠れている帯枕の紐を探します。
*白い紐で、ガーゼで覆われていることも多いです。
2.他の人に押してもらうなどで、帯を背中に着けた状態にし
帯枕の紐をしっかり結び直します。
3.帯枕の紐を再び帯の中にしまいます。 *下の方に送ると胸が苦しくなりません。
帯揚げが仕上がった時より出てきている、取れてしまった
着る時に一番最後に整えるところなので、時間が無くてしっかり整えられないこともありがちですね。きつく結び過ぎると動いているうちに上がってきてしまって帯と隙間ができます。また緩いと帯にかぶさる形で出てきたり‥少し崩れても目立ってしまうところですので、ちょうどよい強さでスッキリ整えましょう。
ー直し方ー
1.動いているうちに帯の上にある飾り布(帯揚げ)が上がってきた時は
帯の方へ押し下げます。
2.結びが緩んで垂れてしまっても背中側は帯に挟まっているので大丈夫!
スカーフを結ぶ感じでお好みの形にまとめて帯の中に入れましょう。
☆帯の中にいくつかある紐に巻き付けておくと再発が防げます。
帯締めが緩んで帯の形が崩れている
帯の真ん中にある帯締めは意外と重要な仕事をしています。結び方にもよりますが、帯締めが取れてしまうと帯の形が崩れてしまいます。太め・固めの紐ですので、締めたつもりでも締まっていないことも多いです。結ぶときにお腹を引っ込めて、しっかり結びましょう。ここはきつく締めても帯の上ですので大丈夫です!
ー直し方ー
1.帯の真ん中にある紐(帯締め)が仕上がった時より下がっていたら・・
緩んでいる状態です。まず、後ろの帯の形を整えます。
2.後ろが整ったら、帯締めを左右両側から前に引っ張って、余りを結び直しましょう。
*他の人にサポートしてもらうと結びやすいです。
*結び方が分からなくなってしまったら、蝶々結びでも構いません。
3.しっかり結んだ残りは、上から下に通す、下から上に通す・・などで 輪を作ると
お花のような形が作れます。
着崩れの防ぎ方
ー歩き方ー
着物は裾つぼまりのロング巻きスカートです。
いつものように脚全体で股関節から歩こうとすると巻いている部分が引っ張られ、
着崩れの原因になります。
膝より上は両脚くっつけて膝から下を動かして歩くのが合っています。
ただ、脚がまっすぐの状態では膝から下のみ動かすのは困難だと思います。
少し膝を曲げて重心を低くする(腰を落とす)と膝から下だけ動かせるようになります。
腰を落としてしずしずと歩きましょう!
慣れてくると腰を落としていてもスタスタと歩けるようになります。
ー座り方ー
両足が一緒に覆われていますので、いつものように脚を出して椅子をまたぐことができません。椅子に近づいたら、まず膝を曲げて椅子の高さに近づくよう腰を落としましょう。
さらに上半身を前に倒すとお尻が出ますので、お尻を椅子に乗せます。
それから最後に、両脚を一緒に正面にもってきます。
ーお手洗いー
何重にも覆われていますので、どうやってお手洗いをしたらよいのか?悩まれることでしょう。大丈夫です!何重になっていても、巻きスカートです。
外側から1枚ずつ左右に分けることができます。
振袖の場合、まず長い袖を体の真ん中に重ねましょう。
帯に挟むかピンチor洗濯バサミで挟むと確実です。
それから一番肌に近い布ですべてを包むようすると安心です。
戻すときは内側から順番に下げて整えましょう。
まとめ
今回は未婚女性の第一礼装、振袖について、特徴、着崩れの原因、直し方、防ぎ方について
代表的なポイントをご紹介させていただきました。お困り中の問題と一致する画像はありましたでしょうか?成人式を楽しく過ごす一助となりましたら幸いです。
着物は着るシチュエーションによって種類・素材がまだまだあります。
次回以降も1つピックアップしてご紹介していきますので
是非再訪いただけますと嬉しいです!

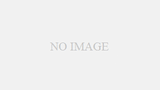
コメント